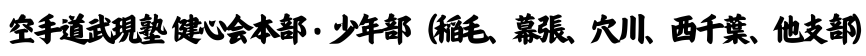終了の合図は終わりではない!| 空手 千葉市
1. はじめに:試合は「合図」で終わるのか?
多くのスポーツでは明確な合図で試合が終わりますが、果たしてそれで本当に「終わった」と言えるのでしょうか?
多くのスポーツにおいて、勝負の始まりと終わりはホイッスルやゴングなどの「合図」で明確に区切られます。サッカーでは試合終了の笛が鳴れば全てのプレーは終了し、バスケットボールでもブザーと同時に試合が終わるのが一般的です。しかしその一方で、プレーが止まっている「ように見えて」も、実際には動いているケースも多々存在します。
たとえば、バスケットボールでは、試合終了のブザーが鳴ると同時に放たれたシュートがリングを通過すれば、それは得点として認められます。つまり、時間が尽きた「その瞬間」まで、プレーは生きているのです。
2. 空手道における「止め!」の意味
当道場での試合ルールと、「止め!」の合図があっても攻撃が有効となる状況について解説します。
これは空手道においても同様です。当道場で実施している試合形式では、「止め!」の合図が入ったとしても、その合図の瞬間に動作が始まっていた攻撃は、明確に「有効打」として判定されることがあります。モーションの途中であれば、それは攻撃として成立するのです。
ルール上はそのように定められており、だからこそ「最後の一瞬まで気を抜くな」という指導を行っています。特に武道においては、「油断する方が悪い」という考えが根底にあります。
油断こそ、最大の隙
3. 油断した者が敗れる武道の世界
武士の時代から現代武道に受け継がれる「油断は最大の敵」という教訓。礼法と警戒心の関係についても触れます。

昔、武士が刀を帯びていた時代。決闘や真剣勝負において、戦いの最中に「降参」や「謝罪」のふりをして相手の隙を誘い、油断させ、背を向けた瞬間に斬りかかるというような事例があったといいます。現代では卑怯に見えるこの行為も、当時の武士たちにとっては「生き残るための知恵」であり、戦術だったのです
このような実戦的な背景があったからこそ、武道における「礼」もまた、単なる形式ではありません。礼の際には、頭を下げながらも相手から目を離してはならない。つまり、見た目の礼儀と共に、心の中では「警戒心」を解かないことが大切とされてきたのです。
「礼に始まり、礼に終わる」と言われる武道の世界。しかしその礼とは、単なる挨拶ではなく、「心を整えると同時に、警戒を保つ行為」なのです。
世界大会の有名な一戦
4. 有名な実例:フグ vs フィリオの一戦
極真空手の世界大会で実際にあった有名な判定と、その裏にある「心構え」の重要性を紹介します。
この「終了しても警戒を解いてはいけない」という教えを象徴するような有名な一戦があります。それは、極真会館が主催する第5回全世界空手道選手権大会でのことです。
スイスのアンディ・フグ選手と、ブラジルのフランシスコ・フィリオ選手の対戦。試合が白熱する中、主審の「止め!」の笛が鳴った直後、フィリオ選手の上段回し蹴りがフグ選手にクリーンヒットし、彼はその場で失神。これに対し、フグ選手の関係者、特にヨーロッパ勢が猛抗議をしたそうです。

「もう笛は鳴っていたじゃないか!」
しかし、その時の最高審判長・大山倍達総裁がこう言い放ったそうです。
「その抗議は受け入れられない!止めの合図でも戦いは終わっていない。油断する方が悪い!」
まさに、この言葉が全てを物語っています。終了の合図があろうと、心の中に隙があってはいけない。それが武道の世界のリアルなのです。
私自身が受けてきた教え
5. 私自身が受けてきた厳しい教え
若かりし頃に師から叩き込まれた教えが、今の指導の柱になっていること。実体験を交えてお伝えします。
このような考え方は、私が若い頃から体験を通して深く身に染みてきたものです。以前所属していた道場でも、師匠から繰り返しこう教えられました。
「終了の太鼓が鳴っても、まだ終わりではない。最後の最後まで気を抜くな。」
この言葉を道場生として、そして後に指導者となってからも、常に大切にしています。

組手の中でも、よく見られるのは「止め!」の声を聞いた瞬間にガードを下ろしてしまい、そこに残った攻撃が入ってしまうという場面。これは、技術の未熟さではなく「心の隙」なのです。終了の声が聞こえても体が動いている、その一瞬に勝負が決まることもある。だからこそ、我々は「最後の最後」まで集中を切らさないよう、稽古を通じて徹底して伝えていかなければなりません。
武道の教えは人生の教え
6. 武道の教えは人生にも通じる
この教えが武道に限らず、社会生活や人間関係、仕事などにも応用できる理由を丁寧に解説します。
この「終わったと思っても終わっていない」という教えは、単なる空手や武道の話ではありません。日常生活においても、仕事でも、人間関係でも、物事が「一区切りついた」と思ったところに落とし穴があることが多々あります。
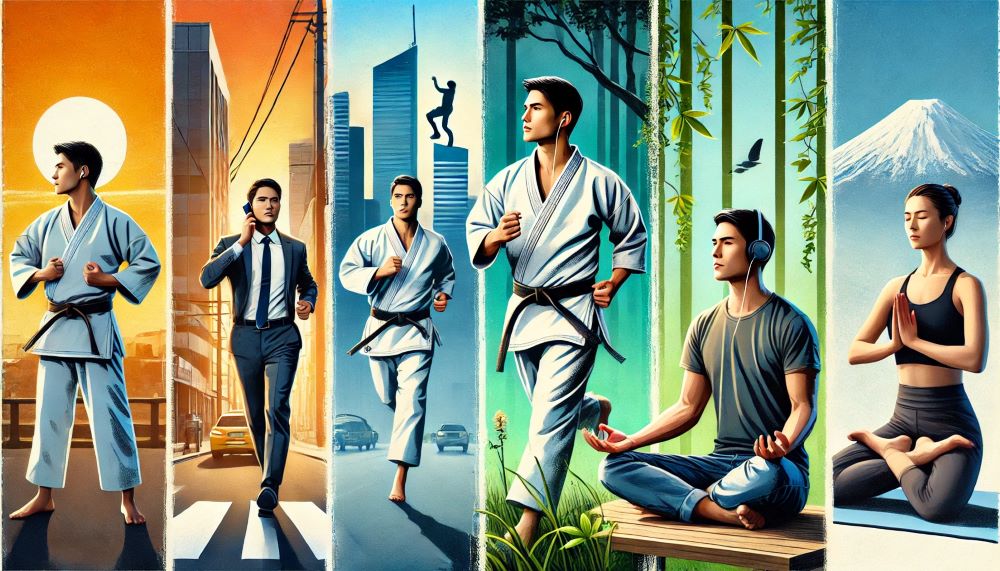
「終わった」と思った瞬間に油断し、トラブルを招いたり、信頼を失ったりすることもある。だからこそ、常に心の準備を持ち、気を抜かず、最後まで責任を持って動くことが大切なのです。
このように、武道で培った精神は、人生そのものに生きる力となっていきます。
最後に:終わりではなく「次への始まり」
7. 終了の合図を「終わり」とせず、次への一歩へとつなげる。それこそが武道における“真の終わり方”。
「終了の合図は終わりではない。」

この言葉は、単にルール上の話ではなく、武道における心の在り方を端的に表現したものです。礼のあとも、試合のあとも、心を緩めるのではなく、自らの動きと相手の動きに対して最後まで責任を持つ。その姿勢こそが、真の強さであり、美しさであり、武道の本質だと思います。
道場に通う皆さんには、こうした精神を少しずつでも体得していってほしい。そしてその姿勢が、日々の生活の中でも生きてくることを願っています。