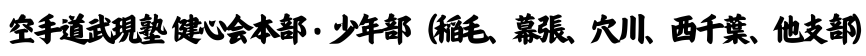オールオアナッシングはあり?なし?| 空手 千葉市
空手道武現塾 健心会代表の石塚克宏です。
最初に私の意見をお伝えしておきます。
すべての事柄に当てはまるわけではありませんが、「やらないよりマシ」という考え方を、私は多くの場面で大切にしています。これは言い換えると、「完璧にできないからやらない」よりも、「少しでもやる方が価値がある」ということです。
空手の稽古においても、まさにそれを実感してきました。最も、最初から途中まで、中途半端でも良いや、と言う考えではやりません。念の為に。
暑い夏、ビールを心の支えに?
ちょっと不謹慎に聞こえるかもしれませんが、選手として現役だった頃、真夏の暑さの中で稽古をするのは、やはりきついものでした。
でも、そんな時私は、稽古後の一杯のビールを楽しみに、汗だくになりながら道場で汗を流していたのです。正直に言えば、「ビールのために稽古をがんばった」と言っても過言ではない日もありました。
もちろん理想を言えば、稽古前はビールのことなんて頭の片隅にも浮かばないくらい、空手だけに集中するべきです。でも、人間はそんなに強くない。
むしろ、「ああ、今日頑張ったら冷えたビールが待っている」というご褒美があることで、ネガティブな気持ちにならず、前向きに道場へ足が向くのです。
実際、稽古が始まれば、空手に集中してビールのことなんかすっかり忘れていました。でも、全身びしょ濡れになった道着を脱ぎ、風呂に入ってから飲む一杯は、それはもう格別の味でした(笑)

継続のチカラ
話が少し逸れてしまいましたが、私が本当に伝えたいのは、「完全な稽古で無くとも継続することこそが強さにつながる」ということです。
どれだけ高い技術を持っていても、それを維持・向上するには継続しかありません。そしてその継続の中にこそ、精神の成長や、自分自身との向き合いがあるのです。
私はこれまで多くの道場生を見てきました。最初は意気込んで道場に通い詰めるものの、数ヶ月後にはパッタリと来なくなる人もいれば、地道にコツコツと続けて、気が付けば何年も道場に通い、黒帯まで取得する人もいます(今の日曜クラスのおじさん達です。30年くらいやってます)。
両者の間に、実は技術的な差は最初の段階ではそれほど大きくなかったりします。しかし、継続できた人だけが、最後には大きな成果を手にするのです。
「自分は才能がないから続かない」という声を聞くこともありますが、私はその逆だと思っています。「続けられることこそが才能」です。毎回の稽古で最高のパフォーマンスを発揮できなくてもいい。今日はキツいな、と思う日があっても構わない。それでも「ゼロにしない」。この心がけが、やがて大きな実力の差となって現れてきます。
たとえば、道場に来て柔軟だけ、基本稽古だけして帰る日があったっていいんです。「行った」という事実が、その人の中に“空手を続けている”という感覚を根付かせます。たとえ小さな努力でも、それを何百回と積み重ねた結果、いつの間にか「強い自分」が形作られているものです。
私自身も、かつては体調がすぐれなかったり、仕事で疲れていたりする日がありました。そんな時、「今日はやめておこうかな」と思うこともあります。でも、道場に足を運んでしまえば不思議と体が動く。そして稽古が終わる頃には「今日も来てよかった」と思えるのです。
この繰り返しが「継続のチカラ」。そしてそれは、一朝一夕で得られるものではありません。
また、継続によって得られるのは技術だけではありません。自分自身に対する信頼も育まれます。「自分は続けられる」「途中で投げ出さない」という自己肯定感が、精神的な安定や強さにつながっていきます。
空手は戦うための術ではありますが、真の意味での「強さ」は、心の持ちようにあります。継続は、その心の強さを育ててくれる最良のトレーニングなのです。
気持ちの切り替えができるようになった
さて、そうして地道に続けていくうちに、私の中で大きな変化が現れました。
以前の私は、どちらかというと「気持ちが乗らないとやらない」「完璧にできないと不満が残る」といったタイプでした。そういう性格だったからこそ、「ビールを楽しみに稽古を頑張る」なんていう方法で自分を動かしていたのです。
でも、気持ち的にキツイ時でも「少しだけで良いから、稽古しよう。」と継続して稽古に向き合い続けていくと、少しずつ自分の中に変化が起こってきます。
まず、稽古を始める前の「気分」に左右されにくくなりました。今日はやりたい気分じゃない…そんな気持ちがあっても、いや、そんな気分そのものが無くなっていました。確かに若い時は気が乗らない時があったとしても、体を動かしているうちに自然とスイッチが入る。稽古に集中できるようになる。この「気持ちの切り替え」が上手くなったのです。
切り替えができるようになった理由は、決して特別な訓練をしたわけではありません。ただ「続けたから」です。続けることで、心と体に“稽古のリズム”が染み込み、自然とオンオフの切り替えができるようになっていったのです。
これは空手だけに限った話ではありません。仕事でも勉強でも、最初からやる気満々で取りかかれる日なんて、そう多くありません。むしろ、やる気がないなぁと思っていても、「とりあえず始めてみる」ことでスイッチが入るという経験は、誰にでもあるはずです。
この切り替え力が身に付くと、人生は非常にスムーズに回るようになります。
なぜなら、「気分が乗らないからやらない」「疲れているからまた今度」といった先延ばしのクセが減っていくからです。やるべきことを“とりあえずやる”という選択ができるようになる。それが、大きな差を生んでいくのです。
また、この切り替え力は、精神的な余裕にもつながります。
「今日は完璧じゃなくていい」と思えることで、自分を追い込み過ぎず、必要なときにしっかりと力を出せる状態を保てるようになります。空手に限らず、日々の生活でバランスを取るためには、この柔軟さが非常に大切です。
私は今でも、稽古の前に「今日はいまいち気分が乗らないな」と思うことがあります。でも、そんな時でも「道場に来ただけでも十分」「柔軟体操だけでもやって行こう」「一本でも多く突きが打てればそれでOK」と自分に言い聞かせて始める。
そうすると、稽古が進むうちに気がつけば汗びっしょり、気分もスッキリして、帰りには「来てよかった」と思える。こうした“感覚の変化”が、まさに「気持ちの切り替えができるようになった」証なのだと思います。
それは単なる技術や習慣ではなく、自分の人生にとっての大きな財産だと今では感じています。
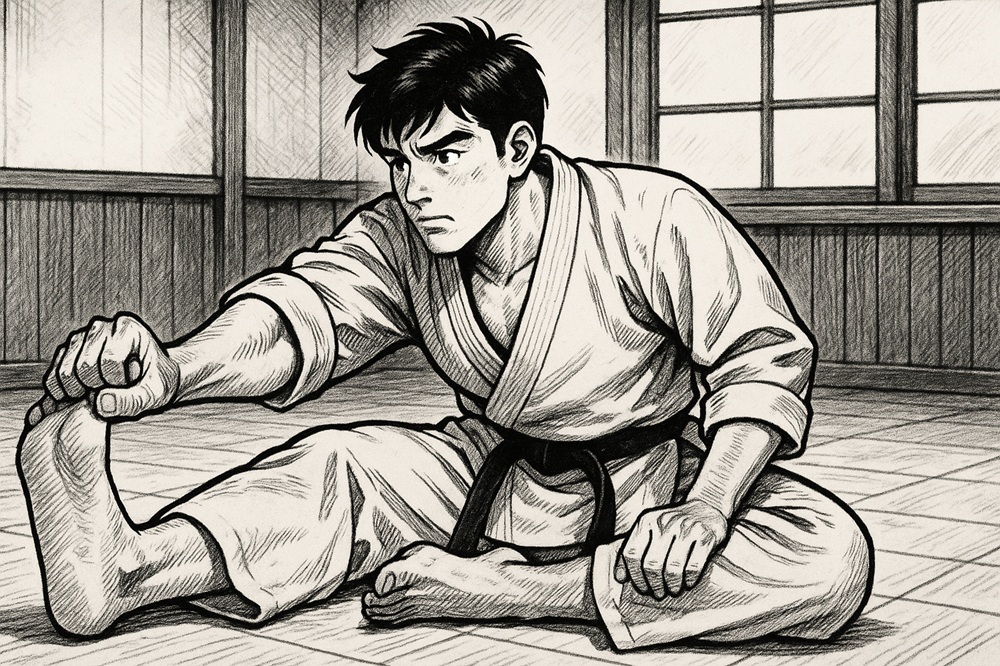
体調不良との付き合い方
もちろん、人間ですから体調が悪い日もあります。
稽古やトレーニングにおいて、体調が万全でないとき、どうするか。これはなかなか難しい判断です。
例えば風邪のひき始めのような日。そんな日は、思い切って汗をかいてスッキリすると、逆に風邪が良くなったりすることもあります。
ですが、「これは無理かな」と思うような日は、潔く休むことも大切です。無理をして悪化させてしまっては元も子もありませんから。
ただ、例えば稽古のサイクルが佳境に入っていて、「今ここで休んだら流れが止まってしまう」という時は、休みたくない気持ちが強くなります。
そんな時は、自分にこう言い聞かせるのです。
「今日は最低限だけやろう。それで体力を温存しよう」
本当に必要なメニューだけをサクッとこなして、終わったらすぐに寝る。無駄なことは一切しない。
そうすると、不思議と次の日には体調が回復して、またトレーニングが予定通りに進められるということがよくあります。
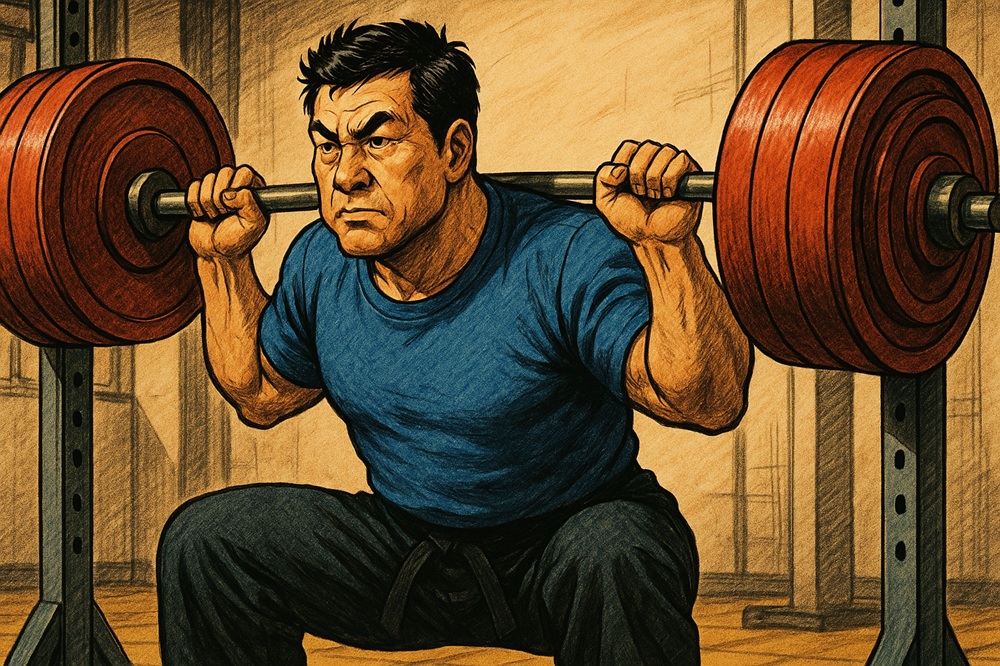
完璧主義の落とし穴?
世の中には、「一度手を付けたら最後まで完璧にやり遂げなければならない」仕事や責任もあります。
そういった場面では、「やらないよりマシ」なんて言っていられません。中途半端は許されず、最後まで責任を持ってやり遂げることが求められます。
私も、仕事や責任ある立場では、そういう姿勢で臨んでいます。
ただし、稽古やトレーニングにおいては、少しだけ考え方を変えても良いのではないかと思っています。
なぜならば、全メニューをやらないと気が済まない、気分が悪い、だったら最初から何もやらない、休む。となると前にも書いたと思いますが、ズルズルと休む癖が出来てしまう可能性があります。その結果、空手やトレーニングから遠ざかり永遠に戻らない事もありうるからです。
体調が万全でなかったり、時間が取れなかったりする日は、「完璧でなくてもやる」。その意識が、継続につながります。
「今日はやめておこう」と思ったその一歩を踏み出すかどうか。たとえ10分でも15分でも身体を動かせば、「やった」という達成感が生まれ、リズムが途切れません。
そしてそれが結果的に、長い目で見れば「大きな成果」へとつながっていくのです。
オールオアナッシングを超えて
「オールオアナッシング(All or Nothing)」という言葉には、潔さや覚悟を感じる響きがあります。
「やるなら全部」「できないならやらない」
そんな考え方も、時には必要です。特に勝負の世界では、全てをかける覚悟が必要な場面もあるでしょう。
しかし、日常の稽古やトレーニングでは、「オール」で無くて良い時はちょこちょこあると思います。勿論、多くの場合は予定時間通り全てをこなす必要がありますけどね。
完璧にできなくても、ほんの少しだけでも「続けること」に意味がある。私は、そう信じています。
「今日は半分しかできなかった」ではなく、「半分はできた」と考える。そんなポジティブな視点を持つことで、日々のモチベーションは保たれ、結果として自分の成長につながります。

おわりに
何もやらないより、ちょっとでもやった方が良い。
この考え方が、私の稽古人生を支えてくれました。そして今でも、変わらず私の中にあります。
もちろん、状況によっては「オールオアナッシング」の精神で挑まなければならない時もあります。それはそれで大事な経験です。
でも、日々の鍛錬や継続においては、「やらないよりマシ」という柔軟な考え方が、多くの人にとって継続の助けになるのではないでしょうか。
これを読んでいるあなたが、今日「やるか、やらないか」で迷っているなら——
10分だけでも、何かをやってみましょう。
それが、あなたの明日を変える第一歩になるかもしれません。