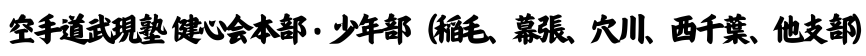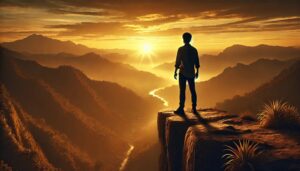人の動きには大きく分けると4つある。4スタンス理論 | 空手 千葉市
はじめに

「みんな動きが違うって知ってた?」と聞かれたら、驚く人も多いかもしれません。でも実は、私たちの体の動かし方には個人差があり、大きく4つのタイプに分類できるんです。
例えば、友達と同じ運動をしているのに、得意な動きや疲れやすさが違うと感じたことはありませんか? それは体の使い方が異なるからかもしれません。
このコラムでは、そんな「4スタンス理論」について簡単に解説します。自分に合った動き方を知ることで、スポーツや日常生活がもっと快適になりますよ! また、無理のない動きをすることで、体への負担を減らし、怪我の予防にもつながります。
さっそく、自分の体の動き方を知るための旅を始めましょう!
人の動き方は4つに分かれる!4スタンス理論とは?

「4スタンス理論」とは、人の体の使い方を4つのタイプに分けて考える理論です。この理論によると、人それぞれ重心の置き方や体の動かし方が異なり、それに合わせた動きをすることで、よりスムーズに体を動かせるようになります。
例えば、スポーツ選手でも同じトレーニングをしていても、成果の出方が違うのは、この動きの違いが関係していることが多いのです。
また、日常生活においても、歩き方や立ち方、物を持ち上げる動作などが人によって異なります。この理論を知ることで、自分に合った体の使い方を理解し、より効率的に動くことが可能になります。
実際に、プロスポーツ選手の多くがこの理論を取り入れ、自分に最適なフォームやトレーニングを見つけることで、パフォーマンスの向上を図っています。
では、次に4つの動き方のタイプを詳しく見ていきましょう。
4スタンス・マトリックス!

それでは、4スタンス理論の4つのタイプを具体的に見ていきましょう。※ここで説明する「重心」とは体重が乗っている場所ではありません。例えばカメラの三脚で説明します。カメラの重量は三脚に三等分して乗っていますよね?しかし、カメラの重心はカメラの真下です。これと同じ理屈です。ちゃんと調べないと自分では分かりません。
A1タイプ(コンパクトでうねるような動き。イチロータイプ)
- (重心が土踏まずの中の爪先内側寄り)
- 軸 みぞおち『内(腹側)』、ひざ『内(膝の前側)』、土踏まず
- 可動部位 首付け根、肩、股関節、手首
- キーワード 前脚軸、曲線的な体幹回転、上昇、人差し指、閉じ、胸側、クロス
A2タイプ(コンパクトでダイレクトな動き。王貞治タイプ)
- (重心が土踏まずの中の爪先外側寄り)
- 軸 みぞおち『外(背中側)』、ひざ『外(膝の裏側)』、土踏まず
- 可動部位 首付け根、肩、股関節、手首
- キーワード 前脚軸、曲線的な体幹回転、上昇、薬指、開き、背中側、パラレル
B1タイプ(ダイレクトでダイナミックな動き。長嶋茂雄タイプ)
- (重心が土踏まずの中の踵内側寄り)
- 軸 首付け根『外(背中側)』、股関節『外(お尻側)』、土踏まず
- 可動部位 みぞおち、肘、膝
- キーワード 後脚軸、直線的な体幹回転、下降、人差し指、閉じ、背中側、パラレル
B2タイプ(ダイナミックでうねるような動き。松井秀喜タイプ)
- (重心が土踏まずの中の踵外側寄り)
- 軸 首付け根『内(喉側)』、股関節『内(鼠径部側)』、土踏まず
- 可動部位 みぞおち、肘、膝
- キーワード 後脚軸、直線的な体幹回転、下降、薬指、開き、胸側、クロス
自分の動き方を知る方法
では、自分がどのタイプなのかを知るにはどうすればいいのでしょうか?簡単なセルフチェックを紹介します。
注意点は「どちらも違和感なく出来る」、ではダメです。自分の身体の声を敏感に聞く事が大事です。
チェックポイント
- リラックスして立って膝を曲げずに前屈。その時に手を太ももの前面に触りながらスムーズに出来る人はAタイプ。モモ裏を触りながらの方がスムーズに出来るのはBタイプ。
- リラックスして仰向けになり、片膝を両手で抱え込む。その時に膝の皿の表を持った方が楽な場合はAタイプ。膝裏を抱え込んでやった方が楽な場合はBタイプ。
- 椅子に浅く座る。片腕を肩の高さで真っ直ぐに出す。人差し指と親指でわっかを作り、わっかを上に向ける。そのまま、腕を水平に外側へ回す。一旦、腕を下ろしてリラックス。その後、同じように薬指でわっかを作り、腕を水平に外側へ回す。人差し指で回した方がスムーズに出来る場合は1タイプ。薬指の場合は2タイプ。
パートナーがいる場合は後ろから、腕を出した肩甲骨を囲むように両手で軽く押さえて行った方がより精度が増す。 - 腕の前まわし、リラックスして正しく立ってから、腕を5回ほど回します。特に頭がブレずにスムーズに出来る方が自身のタイプです。
前回し。上から下へ胸側から背中側へ回す方がスムーズに出来る人は1タイプ。
後ろ回し。逆に下から上に胸側から背中側へ回す方がスムーズに出来る人は2タイプ。
パートナーがいれば横から頭などがブレて無いかチェックして貰う。
このチェックを試してみて、自分がどのタイプに近いかを知ることが大切です。
しかし、あくまでもセルフチェックなので目安としておきましょう。正確に知りたい方は資格を持っているレッシュ・トレーナーに判定して貰うのが良いでしょう。
4つの動き方をスポーツや日常生活に活かす
4スタンス理論を知ると、スポーツや日常生活での動きがよりスムーズになります。
- スポーツのパフォーマンス向上
自分の体に合った動き方を知ることで、無駄な力を使わずに最大限のパフォーマンスを発揮できます。例えば、野球のバッティングやゴルフのスイングなども、自分のスタンスに合ったフォームを意識することで、より安定したプレーが可能になります。 - 日常動作の改善
歩き方や姿勢を見直すことで、腰痛や肩こりを防ぐことができます。階段の昇り降りや長時間のデスクワークでも、自分の体の動かし方を意識することで、負担を軽減できます。 - 怪我の予防
無理のない動きをすることで、関節や筋肉の負担を軽減できます。例えば、ランニング時のフォームを自分の動き方に合わせることで、膝や足首への負担を減らすことができます。また、スポーツだけでなく、重い荷物を持つ際の姿勢も改善され、腰痛のリスクを軽減できます。
4スタンス理論を理解し、自分に合った動き方を意識することで、日常生活でもより快適に過ごせるようになります。
4スタンス理論を学ぶメリット
この理論を学ぶことで、以下のようなメリットが得られます。
- 自分に合ったトレーニングができる
自分の動きのタイプを理解すれば、無理なく効果的なトレーニングができ、怪我のリスクも減らせます。特にスポーツ選手にとっては、最適な動きを意識することでパフォーマンスの向上につながります。 - 体の使い方をマスターして効率的に動ける
日常の動作がスムーズになり、余計な力を使わずに済むようになります。例えば、長時間のデスクワークによる肩こりや腰痛の軽減にも役立ちます。 - スポーツだけでなく、日常生活でも役立つ
買い物時の荷物の持ち方や、階段の上り下り、立ち姿勢なども改善され、疲れにくい体を作ることができます。
特に成長期の子どもたちにとっては、自分に合った動き方を知ることが、運動能力の向上につながります。また、運動が苦手な子どもでも、自分に合った動きを知ることで運動への苦手意識が減り、自信を持って取り組めるようになります。
さらに、高齢者にとってもこの理論は有効です。正しい重心の位置を意識することで、転倒のリスクを減らし、日常生活での動作が楽になります。健康寿命を延ばすための一つの手段としても活用できるでしょう。
まとめ:自分に合った動きを知って、もっと快適に!
私たちの体の動かし方には個性があります。4スタンス理論を理解し、自分の動きに合ったトレーニングをすることで、より効率的に体を動かせるようになります。
例えば、スポーツをしている人は、この理論を活かして自分に合ったフォームを見つけることで、無理なくパフォーマンスを向上させることができます。逆に、普段あまり運動をしない人も、この理論を知ることで日常動作の負担を軽減し、姿勢の改善や疲労の軽減につなげることができます。
また、子どもや高齢者にとってもこの理論は非常に有益です。子どもは、自分の動きのタイプを早く知ることで、運動がより楽しくなり、成長期の体づくりに役立ちます。一方、高齢者は、自分に合った姿勢や歩き方を意識することで、転倒のリスクを減らし、健康寿命を延ばすことができるかもしれません。
スポーツをしている人も、日常生活で体をスムーズに動かしたい人も、ぜひこの理論を活用して、より快適な毎日を送りましょう!
よくある質問(Q&A)
Q:どのタイプが一番優れているの?
A:どのタイプも優劣はなく、それぞれに適した動き方があります。
Q:自分の動き方を知った後、どう活かせばいい?
A:スポーツや運動の際に、自分の動きに合ったフォームやトレーニングを取り入れると効果的です。
Q:子どもや高齢者にも当てはまるの?
A:はい。年齢に関係なく、すべての人に適用できます。特に子どもは早いうちに自分の動きを知ることで、運動能力が向上しやすくなります。
4スタンス理論を知ることで、自分に合った動きを理解し、もっと快適に生活することができます。ぜひ、この理論を日常に取り入れてみてください!