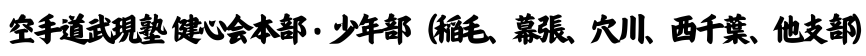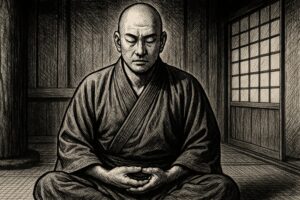千葉市・空手道武現塾 / 怪我について| 空手 千葉市
怪我とどう向き合うか 〜身体のケアも稽古のうち〜
空手道武現塾・健心会本部
代表 石塚克宏(千葉市)
はじめに
千葉市の空手道武現塾 健心会の石塚克宏です。
今回は「怪我」についてお話ししたいと思います。
ここで言う怪我とは、精神的なものではなく身体的な怪我のことです。
空手に限らず、スポーツをしていれば怪我とは切っても切れない関係にあります。
しかし、「怪我をどう受け止め、どう向き合うか」でその後の成長は大きく変わります。
これは私自身の経験からも断言できます。

空手で多い怪我とその種類
空手道の稽古で多いのは、まず打撲や突き指。
これらは日常的なレベルで起こりやすい怪我です。
その他にも、捻挫、切り傷、擦り傷、骨折などもあります。
また、見落とされがちですが、**ギックリ腰(急性腰痛症)**も空手家にとっては要注意です。
ギックリ腰は「腰の捻挫」と言われます。
経験した方なら分かるでしょうが、これは本当に痛い。
ヨーロッパでは「魔女の一撃」と呼ばれているほどです。
その表現の通り、まさに“突然襲いかかる痛み”です。

若い頃の自分に言いたいこと
私自身も若い頃に何度も痛い目を見てきました。
特に19歳の時と26歳の時のギックリ腰は、今でも鮮明に覚えています。
当時は「鍛える」ことばかりに意識が向いていて、身体のメンテナンスを殆どしていませんでした。
確かに、練習量は今の何倍もありました。
しかし「量」ばかりで「質」や「ケア」が伴っていなかった。
今振り返ると、これが最大の反省点です。
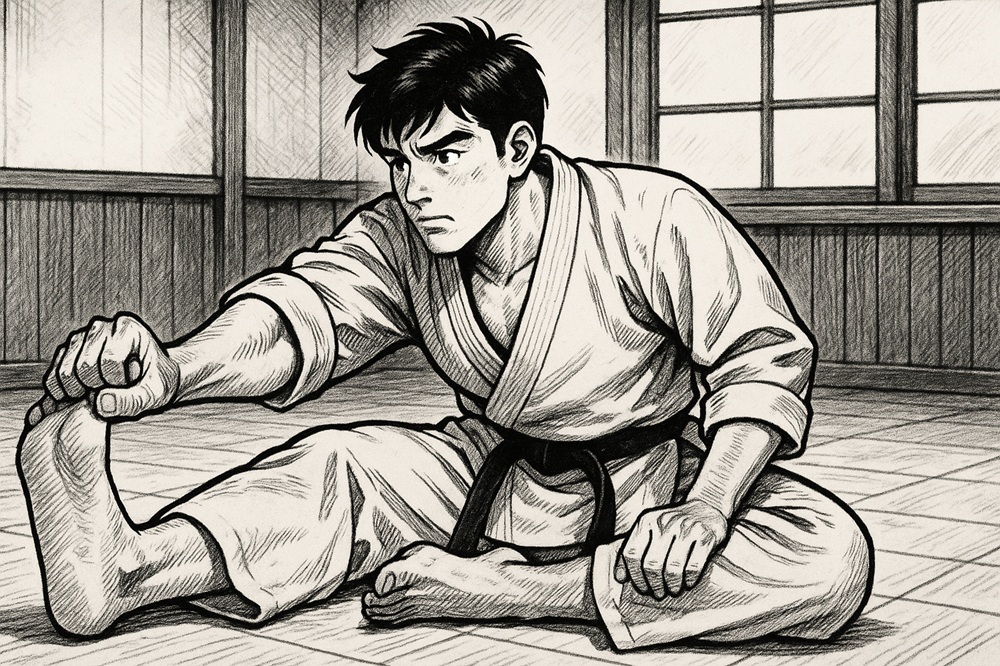
クールダウンのストレッチはやっていましたが、それだけでは足りませんでした。
若くてお金がないとはいえ、月に一度整体に行く余裕はありました。
でも、「まあ大丈夫だろう」と放置してしまったのです。
その結果、30歳を前にしてぎっくり腰ではありませんが、首のヘルニアを発症。
しびれや痛みで稽古もままならず、ようやく自分の身体の扱い方を学び始めました。
この時、道場生の紹介で整骨院に通い始めたのが転機でした。
そこから身体の構造や回復の大切さを学び、
さらに、現在お世話になっている「ノーリミッツ」でトレーニング理論を学ぶようになって、
ようやく「鍛える」と「休める」のバランスを理解できるようになったのです。
若い人へ伝えたいこと
ここで、若い世代へ強く言いたい。
「身体のケアを怠るな!」
「身体のケアは稽古と同じくらい重要だ!」
これは私が身をもって痛感したことです。
怪我をしてからでは遅い。
痛みを通して初めて気づく人が多いですが、怪我をしない努力こそが最も重要な稽古です。
かつて道場の壁に貼っていた「空手家職人十ヶ条」に、こういう言葉がありました。
「日々の稽古、身体のケア、試合、その全てを楽しめ。そして好きになれ。」
まさにその通りです。
稽古もケアも、そして試合も“自分を高める時間”。
どれか一つでも欠けると、結局は自分の可能性を狭めてしまいます。
怪我をした時の基本対応
それでも、どんなに気をつけていても怪我は起こります。
では、怪我をしたらどうすべきか。
まず大原則として、無理はしないこと。
「このくらい大丈夫だろう」と甘く見た結果、悪化して長引くケースは数え切れません。
私もその一人でした。
しかし一方で、軽傷なのに過剰に休みすぎるのも考えものです。
強くなりたいなら、**「できる範囲でやる」**ことが大事です。
ヨーロッパの諺に「賢者は歴史から学び、愚者は体験から学ぶ」とあります。
怪我の世界では、まさにこれ。
できれば、他人の経験から学ぶべきです。
年長者や経験者の話は、思っている以上に価値があります。

「とりあえず言われたことはやってみる」
——これが意外と一番の近道です。
怪我の原因は「痛い箇所」だけではない
怪我をした時、多くの人は痛みのある部分ばかりに注目します。
しかし、実際の原因は別の部位にあることが非常に多いのです。
例えば、「腰が痛い」と言っても、
原因が足首や首にある場合もあります。
身体は一つの“つながったシステム”で動いているため、
一箇所の不具合が他の部分に負担をかけて痛みとして現れるのです。
ですから、痛い箇所だけに湿布を貼っても根本解決にはなりません。
信頼できる整体師やドクターを見つけることが何より重要です。
ただし、これも実際に会って話してみないと分かりません。
紹介でもいいですが、最終的に「この人に任せよう」と判断するのは自分自身。合う、合わない、は誰でもありますからね。万人に効果抜群の整体師…、いるでしょうが、まずお目にかかれません。ある程度は良くなる…、程度はいますが…。
そうやって“自分の身体を託せる専門家”を見つけることが、
長く武道を続ける上での鍵になります。
打撲・骨折・その他の怪我の実例
私自身、これまでに色々な怪我をしてきました。
中でも多かったのが打撲と肋骨の骨折です。
打撲の場合は、まずは**アイシング(冷却)**が基本(コラムの一番最初にありますね)。
そして、痛みが強い場合は迷わず医療機関へ。

骨折の場合は、とにかく「固定」が最優先です。
私も過去に4〜5回ほど肋骨を折りました。
最初の頃は、息をするだけでも痛かった。
しかし、少し回復してきたら出来ることだけを続けるようにしました。
胴体にコルセットを巻いても出来るレッグエクステンション(脚の筋トレ)カールなどを中心に行い、
痛みが軽くなってきたらマススパーリングに戻りました。
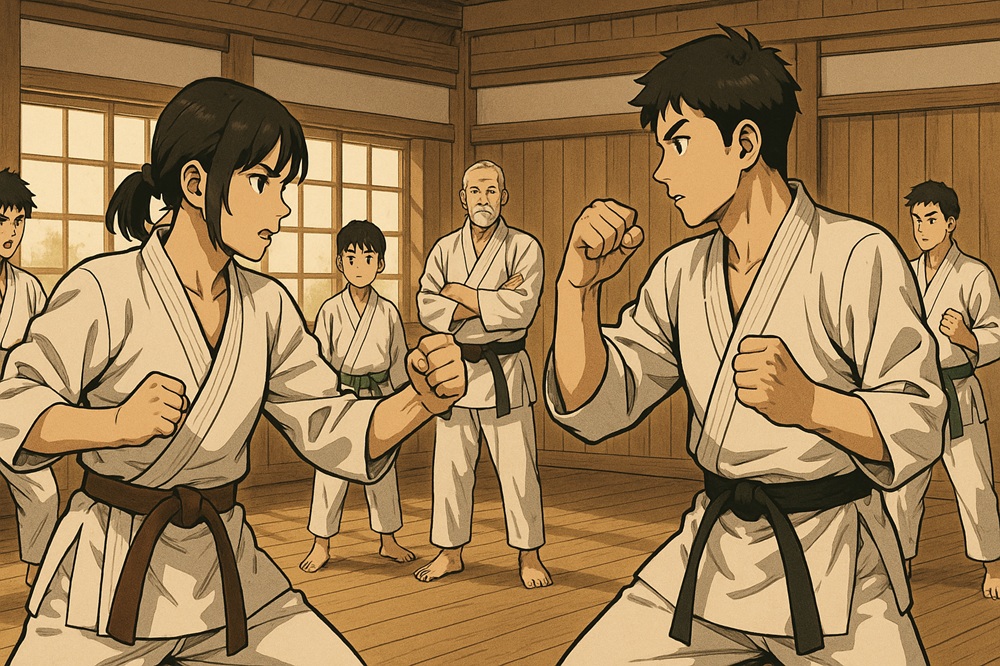
この「できる範囲でやる」という考え方が、結果として回復を早めたように思います。
怪我をしたからといって全てを止めてしまうのではなく、
「動かせる部分を動かす」ことが、リハビリにもなるのです。血流も良くなりますし、成長ホルモン分泌の促進にもなります。
怪我と“心”の付き合い方
もう一つ大事なことがあります。
それは、「怪我に対して過敏になりすぎない」ということ。
もちろん無理は禁物ですが、必要以上に怖がってしまうと、
体は余計に硬くなり、結果として怪我を招きやすくなります。
つまり、良い意味で鈍感になることが大切です。
痛みを冷静に観察し、「今できることは何か?」を考える。
そうすると、怪我の期間も前向きに過ごせます。
これは稽古だけでなく、人生にも通じます。
困難にぶつかっても、「できることを探す」「少しでも進む」——
この姿勢が成長の源です。
トレーニングとケアのバランスを学ぶ
今の私は、稽古と同じくらい**リポーズ(身体調整の為の柔軟体操)**を重視しています。
毎日最低20〜30分は行っています。時間に許す時は1時間近くも。
若い頃の自分に「せめて20分でもやれ」と言いたいくらいです。
リポーズを始めてからは、身体の動きがスムーズになり、
疲労の抜けも格段に良くなりました。
つまり、「休むこと」も立派な稽古なのです。
※写真はリポーズの中の「Cの字ポーズ」

空手を長く続けるためには、
鍛える時間と整える時間の両方が欠かせません。
稽古・睡眠・食事・メンテナンス。
この4つが揃って初めて、真の「強さ」が育ちます。
まとめ 〜できる理由を考えよう〜
怪我は誰にでも起こるものです。
しかし、怪我をした時に「なぜ自分だけが…」と嘆くのではなく、
「この経験から何を学べるか」を考えることが大事です。
怪我をした原因。対策。
怪我を通して、身体の仕組みを知り、
人の助けを受け、そして自分を見つめ直す。
それもまた、武道の修行の一部です。
だからこそ、怪我をしたら焦らず、
「今できること」を積み重ねていきましょう。
「できない理由ではなく、できる理由を考える。」
この姿勢が、あなたの空手をさらに強く、そして長く続けさせてくれます。
空手の稽古は「強くなるための道」であると同時に、
「自分の身体と心を知る学びの場」でもあります。
どうか皆さんも、怪我と上手に付き合いながら、
一歩一歩、前へ進んでいってください。