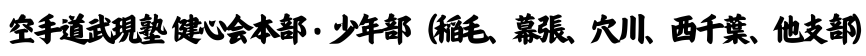技は“盗む”ものだ。教わるだけではモノにならない。――技を習うな、見て盗め| 空手 千葉市
はじめに
空手の稽古において、誰もが最初は何もわからないところから始まります。立ち方、構え方、礼の仕方――すべてが未知の世界です。ですから、最初のうちは先輩や先生に教えてもらうことが必要不可欠です。何も知らない者が、いきなり自己流でやっても身につくものはありません。基礎を学ぶ段階では「教えられること」が非常に大切です。
しかし、ある程度動けるようになってきたら、そこからは「教わる姿勢」だけでは上達が停滞します。むしろ、成長を止めてしまうことすらあるのです。
「考える力」を止めてはいけない
空手の技術は、言われたことだけを反復しているだけでは深まりません。もちろん繰り返しの稽古によって身体に染み込ませることは大切です。ただし、そこに「考え」が伴っていなければ、上辺だけの動作になってしまいます。
「どうしてこの技は効くのか?」
「なぜこの構え方なのか?」
「どうしたら自分の動きに取り入れられるのか?」
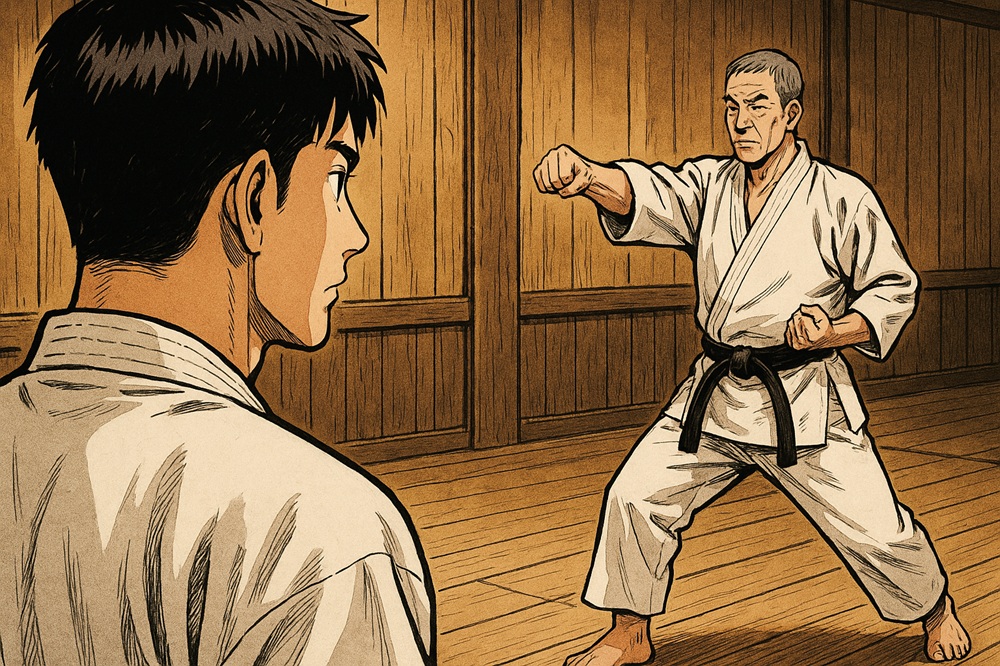
こういった問いを自ら持ち、技を“観て”、“真似して”、“研究する”姿勢がなければ、空手の深みには到達できません。師匠や先輩の技を見る。その動きを盗む。そして自分の身体に落とし込む。これが本当の意味で技を「自分のモノ」にするということなのです。
私が若い頃に学んだこと
私が若い頃、ある道場生からこんな質問を受けたことがあります。
「先生、下段回し蹴りを出すと、カウンターで顔面パンチをもらってしまいます。どうすればいいんですか?」
そのとき、私はつい反射的に答えを教えてしまいました。「こうすればいい」と一つのやり方を提示したのです。もちろんそれ自体は間違ってはいなかったのですが、結果的にその道場生は、私の言ったやり方しかやらなくなってしまいました。
その技しか使わなくなると、戦いの幅が狭くなります。応用もできない。結果的に、その場しのぎの対応力しか育たなかったのです。
一方で、自分なりに試行錯誤を繰り返し、何通りものやり方を考えて実戦で試した者は、状況に応じて臨機応変な対応ができるようになっていきます。なぜなら、“考えた技”は自分の中に深く根を張るからです。そこから独自の工夫が生まれ、引き出しが増え、柔軟性と応用力が養われるのです。
観察し、真似し、盗め
道場ではよく「技は盗め」と言います。もちろんこれは勝手に技を“横取り”しろという意味ではありません。意味するのは、「自分から積極的に学ぶ姿勢を持て」ということです。
たとえば、師匠や先輩が何気なくやっている構え、タイミング、間合いの取り方――それらには膨大な経験が詰まっています。言葉では説明できない“感覚”が込められているのです。そこに気づき、観察し、何度も真似し、自分の身体を通して理解していく。これが「盗む」ということなのです。
技を盗むには「観る力」が必要
技を盗むには、ただ見ているだけでは足りません。「観る」ことが必要です。
観るとは、意識して注意深く見ること。何がどう動いているのか、自分と何が違うのか。そこを見極める力がなければ、盗むことはできません。
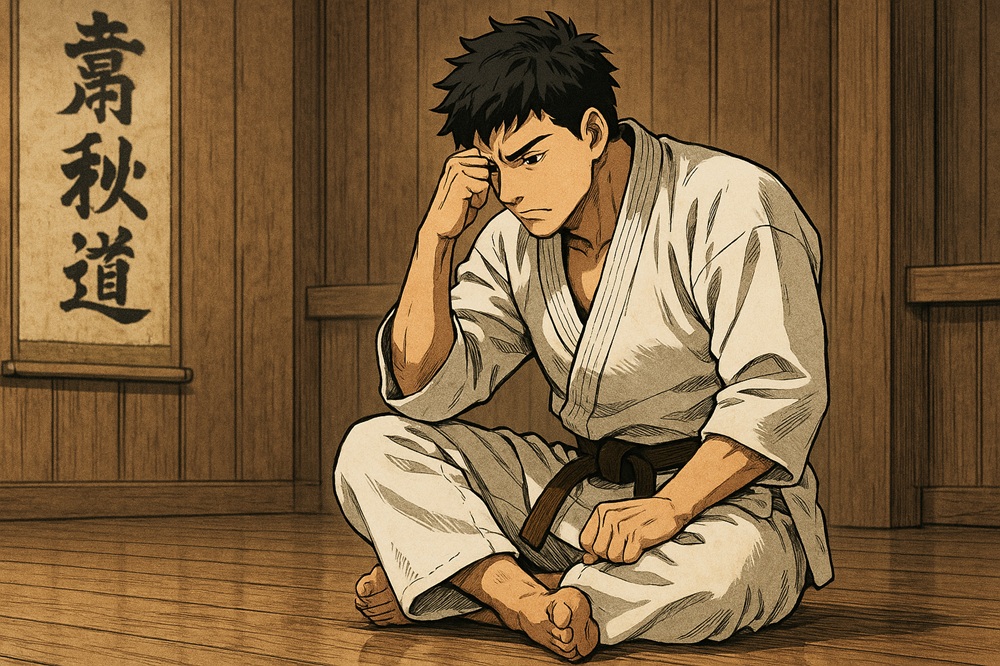
そして、真似をしてみる。上手くいかない理由を考える。上手くいったときの感覚を覚える。こうしたプロセスを何度も繰り返すことで、はじめてその技が“自分の技”になっていきます。
教えることの難しさと、教わる側の姿勢
冒頭に述べたように、初心者には丁寧な指導が必要です。ただし、ある程度動けるようになったら、すべてを細かく教えるのではなく、自分で気づかせる工夫が必要です。
そして、教わる側も「分からないから教えてほしい」とすぐに答えを求めるのではなく、「自分で試して考えてみる」ことが必要です。これはとても大切な意識の持ち方です。
アインシュタインの名言にも学ぶ
私が特に印象に残っている言葉があります。物理学者アインシュタインが言ったとされる言葉です。
「7歳の子どもに納得できる説明ができなければ、それは教える側が本当に理解していない証拠だ。」
これは教える立場の者にとって非常に重みのある言葉です。難しい言葉で煙に巻くような説明では、本当に伝わったことにはなりません。本当に理解していれば、シンプルで分かりやすい言葉で伝えられるはずなのです。
逆に言えば、教わる側も、シンプルな説明の中から本質を汲み取る力が必要です。そして、そこから「なぜそうなのか?」と自分なりに深掘りしていくことで、より技術が磨かれていきます。
まとめ:教わるな、盗め
初心者のうちは教わることが大切です。しかし、ある程度動けるようになったら、「教わる」だけでは足りません。そこから先の成長は、「観て」「盗んで」「自分で考えて」「実践する」中にあります。
型を見て真似する。動きを見て盗む。構えを見て自分に落とし込む。――そういった姿勢があってこそ、空手の技術は真に自分のものになります。
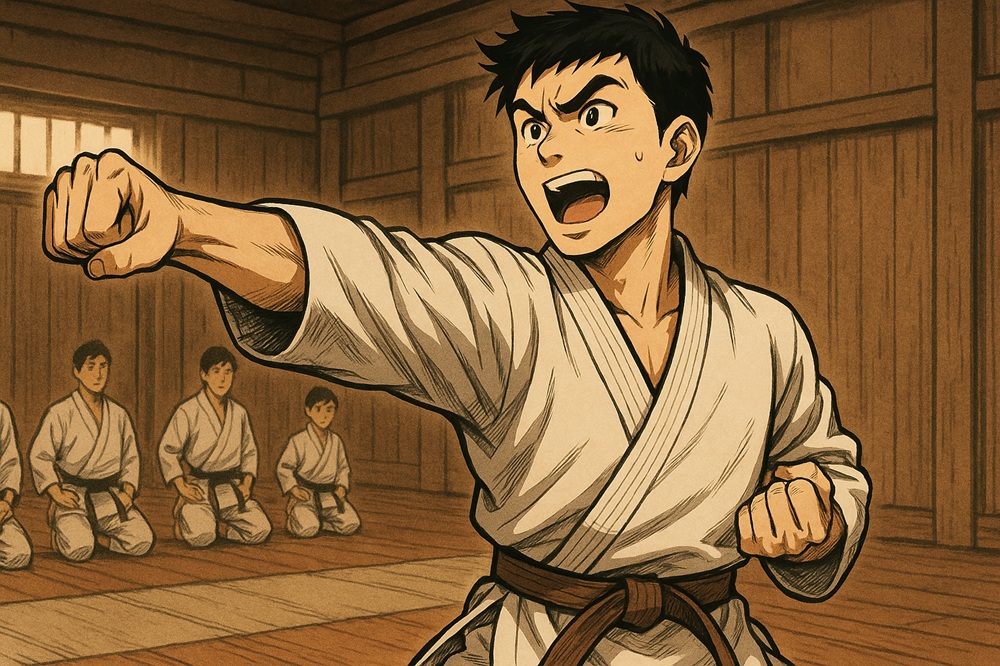
技は“盗む”ものだ。
教わるだけではモノにならない。
「技を習うな、見て盗め」――この言葉の意味を、ぜひ日々の稽古の中で感じてください。
押忍。