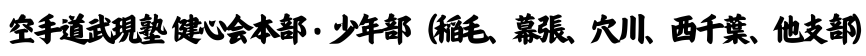教える事は己の技量を向上させる| 空手 千葉市
指導の価値に気づいた原点
この言葉の意味を、私は若い頃に身をもって体感しました。
私が空手を学び始めた当時の道場では、ある独特なルールがありました。
それは、白帯から青帯に上がったら、すぐに白帯の指導にあたるというものです。

青帯以上の色帯や黒帯の者たちは、10分ずつ交代しながら、基本稽古や移動稽古、防御の型、そして約束組手までを、白帯の生徒たちに教えるのが習わしでした。
もちろん、その日その日の参加者によって、指導する内容は異なります。ある日は立ち方、ある日は突きや蹴りの角度、あるいは組手での距離の取り方まで。
その場で即座に対応する柔軟性と理解力が求められるのです。
教えて初めて気づく“分かっていなかった自分”
最初は、正直なところ戸惑いしかありませんでした。
誰かから「教え方」を教わったわけでもなく、何もわからないまま、いきなり白帯の前に立つことに。見よう見まねで説明する日々が続きました。
ところが、教えているうちに、不思議なことが起こります。
自分では「理解しているつもり」だった技や動作が、実は曖昧だったことに気づくのです。
いざ誰かに説明しようとすると、言葉に詰まる。「なぜこの動作をするのか」「なぜこの姿勢なのか」。
自分の中で明確に整理されていなかったことが、教えることによってあぶり出されていきます。
教えることで技術は“自分のもの”になる

また、繰り返し同じことを教えることで、自然と自分の中にも定着していきます。
「突きはこの角度で」「足の位置はここ」「構えたら肩の力は抜いて」――そうして繰り返し言葉にすることで、自分の体と頭の中に技術がしみこんでいく。
これは、「教えることは、最高の反復練習になる」ということです。
教えるという行為は、相手のためだけでなく、自分自身の精度を上げる最高の手段なのです。
大切なのは「伝わる言葉」を選ぶこと
もう一つ、私が強く実感したのは、言葉の選び方の重要性です。
自分が理解していても、難しい専門用語や抽象的な表現を使えば、相手には伝わりません。とくに子どもたちが相手であれば、なおさらです。
教える時には難しい専門用語を使うのではなく、簡単な言葉で、簡単な説明で伝える。これが大事だと思います。
あのアインシュタインが、こう語っていたと言われています。
「7歳の子供に納得できる説明ができなければ、それは教える側がちゃんと理解していない証拠だ。」
まさにその通りです。
子どもに伝えることができる、というのはつまり、本質をつかんでいるということ。芯を理解しているからこそ、シンプルな言葉で説明できるのです。
指導の経験は、自分の成長の場でもある
青帯たちが白帯に教える時間は、単なる稽古ではありません。
それは、自分の動きを見直す機会であり、自分の理解度を確認する場であり、そして「相手に伝わるかどうか」を常に試される貴重な時間です。それは黒帯になっても同じです。

指導を重ねる中で、生徒からの質問が、私自身の学びになることも多くあります。
「なぜこうするんですか?」という素朴な疑問に、ドキリとさせられる。言語化できていなかった部分に、教えられることもあるのです。
「教える文化」をこれからも大切に
私の道場では、この「教える文化」をこれからも大切にしていきたいと考えています。
たとえ青帯になったばかりの子どもであっても、教える経験を通じて、自分の空手と向き合ってほしい。
そしてその過程で、技術だけでなく、伝える力・気配り・思いやりも育んでいってほしいのです。
最後に

「教える事は己の技量を向上させる。」
この言葉は、単なる技術向上だけでなく、人間的な成長にもつながると私は信じています。
そしてそれは、教わる側だけでなく、教える側にとってもかけがえのない学びの時間なのです。